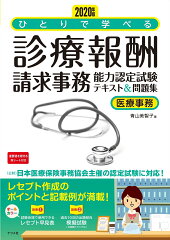-
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
通常の病院内電子カルテの場合,医師がIDとパスワードで電子カルテにログインすると,患者の一覧が表示されるか,患者のID入力欄が表示されます.医師は患者IDを入力すると患者さんのカルテが表示されることになります.
患者一覧が表示される場合は,どの患者データでも開くことができます.患者IDを入力するように要求される場合でも,患者IDをランダム入力すると1/10くらいの割合で,不特定の患者にヒットする可能性があります.
よって,このような病院内電子カルテシステムと同じやり方では,インターネットの上に医療情報を保存することは危険です.
ネットワークの範囲が小さければ,あまり問題になりませんが,インターネットの上で,いつでも何処でも必要なデータにアクセスするためには,患者-主治医関係のある場合のみアクセスできるような仕組みが必要です.でないと,東京の患者データに無関係の北海道の医師がアクセスする可能性があるからです.
インターネットの上に医療データを置いた場合,パスワードを破られるとか,通信時にデータを盗まれるとかの問題の他に,このような医療データへのアクセス権の問題が生じてしまうわけです.
これをどのように回避するかが大きな問題となりました.PR -
2001年末,既にインターネットは普及し,ウェブブラウザにより,様々な情報がホームページに掲載され,私達は簡単に必要な情報にアクセスできるようになっていました.
電子カルテは少しずつ認知されるようになっていましたが,多くの病院では,紙のカルテが使われていました.施設によっては,CTやMRIの画像サーバシステムが動いていましたが,現在ほど普及してはいませんでした.
患者さん達は,CTやMRIを撮影した後,検査した病院から他の病院へ紹介されれば,フィルムを持って移動していました.これは現在でも,大部分,同じような状況です.ところが,画像フィルムを持ってくるのを忘れたり,画像が紹介される医療施設に届いていなかったりということが時にあります.
そんな中,『いつでも,何処からでも必要な時に必要な画像を見ることが出来ないだろうか』と考えた医師がいました.このような事を考えた医師たちは,画像を電子的にネットワーク上に置く方法を研究しはじめました.
ネットワーク上に医療用画像(それと同じような役割をもつ情報)を置く仕組みを,ここでは”医用データ共有システム”と呼ぶことにします.
この医用データ共有システムが,ITカルテ開発のもとになるわけです.
ところが,医療情報をネットワーク上に置いて,いつでも何処からでも見る,ということは非常に危険な事でもありました.この当時,医用データ共有システムの理論的背景は考え出されていなかったわけで,ネットワーク上の医療情報を,いつでも何処からでも見るためには,大きな考え方の転換が必要でした.